ダンサーとしてフリーランスで活動していると、健康保険や年金について「このままで大丈夫?」「会社員のように社会保険に入れないの?」と不安を感じる方も多いはずです。
実は、個人事業主でも条件を満たせば社会保険に加入できる方法が存在します。扶養に入る、法人化する、国保組合を利用するなど、選択肢はいくつかあり、それぞれメリットとデメリットが異なります。
この記事では、フリーランスダンサーが選べる社会保険と年金の仕組みをわかりやすく整理し、将来の安心につながる方法を解説します。
会社員とフリーランスの違いを知ろう
会社員として働いている場合、健康保険や厚生年金といった社会保険制度には、自動的に勤務先を通じて加入します。保険料は給与から天引きされ、加入や変更の手続きも会社の総務部門が代行してくれるため、自分で意識する機会は少ないかもしれません。
一方で、フリーランスや個人事業主として活動するダンサーの場合は状況が異なります。
自ら市区町村役所や年金事務所に出向き、国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を納付する義務があります。未加入のまま活動を続けると、将来の年金受給額が減少するだけでなく、病気やケガをした際に医療費の自己負担が大きくなり、生活に重大なリスクを抱えることになります。
制度をわかりやすく整理すると、次のようになります。
- 会社員:厚生年金+健康保険(いわゆる二階建て構造)
- フリーランス(個人事業主):国民年金+国民健康保険(一階建て構造)
この違いをまず理解することが、フリーランスとして安心して活動を続けるための第一歩です。
国民健康保険(国保)とは?
フリーランスダンサーが最初に直面するのが「国民健康保険(国保)」です。国保は会社員向けの社会保険に代わる医療保険制度であり、加入手続きは住んでいる市区町村役所で行います。
- 加入先:住民票がある市区町村の国民健康保険窓口
- 保険料の算定方法:前年の所得に基づいて計算されるため、収入が増えれば翌年の保険料が大幅に上がる可能性があります
- 医療費の自己負担割合:原則3割(70歳以上は2割または1割負担)
- 扶養制度の有無:会社員の健康保険にある「扶養制度」が国保には存在しないため、配偶者や子どもも個別に加入・保険料を支払う必要があります
特に注意すべきは「翌年負担の増加リスク」です。例えば、ある年にダンスの仕事が好調で収入が倍増した場合、翌年の国保料も大幅に上がることになります。見落とすと「前年に稼いだはずなのに、今年は保険料の請求が重くのしかかる」といった事態になりかねません。
国保はフリーランスにとって避けられない制度です。計画的に資金を管理し、想定外の負担増に備えておくことが非常に重要です。
(出典:厚生労働省「国民健康保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kokuho/index.html)
国民年金とは?
フリーランスや個人事業主が将来の老後生活を支える年金制度は「国民年金」です。会社員のように厚生年金が上乗せされないため、老後の受給額は相対的に少なくなる点を理解しておく必要があります。
- 納付額:毎月定額で支払う(2025年度時点で約16,000円/月)
- 受給額:満額納付を40年間続けた場合でも、年額約80万円程度(1か月あたり約6〜7万円程度)にとどまる
- 未納リスク:支払いを滞納すると、その期間は将来の受給額に反映されず、結果として受け取れる年金が大幅に減額される
- 追納・免除制度:経済的に困難な場合は「免除制度」や「猶予制度」を利用可能。一定条件を満たせば将来的に追納して年金額を回復することもできる
さらに将来の不安を減らすためには、国民年金基金や**iDeCo(個人型確定拠出年金)**といった上乗せ制度を利用することが有効です。これらは掛金が「全額所得控除」の対象となり、節税効果と将来の年金補強を同時に得られるメリットがあります。
フリーランスダンサーにとって、国民年金は「最低限の老後保障」です。安心して踊り続けるためには、これを基盤にプラスアルファの準備を早めに始めることが大切です。
国保と社会保険の比較表
| 項目 | 国民健康保険+国民年金(フリーランス) | 社会保険(会社員・法人化など) |
|---|---|---|
| 加入主体 | 市区町村が運営 | 会社(法人)、勤務先 |
| 保険料の決まり方 | 前年の所得に応じて計算 | 給与額に応じて計算(会社と本人で折半) |
| 医療費の自己負担 | 原則3割 | 原則3割(高額療養費制度も同様) |
| 扶養制度 | なし → 家族も1人ずつ加入 | あり → 配偶者・子どもを扶養に入れられる |
| 年金の種類 | 国民年金(基礎年金のみ) | 厚生年金(基礎年金+報酬比例部分) |
| 将来の年金額 | 約月額5〜6万円(40年間満額納付の場合) | 報酬比例で増額(平均で月額14万円以上になるケースも) |
| 保障の厚さ | 最低限の保障 | 医療・年金ともに保障が手厚い |
| メリット | 自由度が高い/保険料は収入が低ければ安い | 老後の年金が増える/家族を扶養に入れられる/会社が半分負担 |
| デメリット | 将来の年金が少ない/扶養制度なし | 保険料が高め/法人化や勤務継続が必要 |
(年金額の目安は厚生労働省「年金制度の概要」より算出:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/index.html )
フリーランスでも社会保険に入れる方法
フリーランスは「国民健康保険+国民年金」に加入するのが一般的ですが、条件によっては社会保険制度にアクセスできる手段も存在します。これを理解しておくと、保障を厚くする選択肢が広がります。
家族の扶養に入る
配偶者や親が会社員として社会保険に加入している場合、その扶養に入ることが可能です。
年間収入が130万円未満(パートタイム労働などで一部例外あり)であれば、扶養家族として認定され、健康保険と厚生年金の両方がカバーされます。
ただし「130万円未満」は「税金上の扶養」とは異なる基準であり、収入の種類や継続性によって判定が変わる点に注意が必要です。
会社を設立(法人化)する
個人事業主には社会保険の加入義務はありませんが、株式会社や合同会社を設立すると、代表者が1人でも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することが必須になります。
法人化すると、将来的に受け取れる年金額が増え、医療保障も手厚くなるメリットがあります。
その一方で、会社負担分の保険料も発生するため、実質的な負担額は大きくなる点を考慮しなければなりません。
いいテーマです!
「個人事業のまま」と「会社法人化した場合」のコスト比較を整理すると、読者が「今の自分はどちらが有利か」を判断しやすくなりますね。以下にわかりやすい表を作成しました。
個人事業主 vs 法人化(株式会社/合同会社)の費用比較
| 項目 | 個人事業主(フリーランス) | 法人化(株式会社・合同会社) |
|---|---|---|
| 開業時の費用 | 0円(開業届を税務署に提出するだけ) | 株式会社:約20〜25万円(登録免許税15万円+定款認証5万円+印紙代4万円など) 合同会社:約6〜10万円(登録免許税6万円+定款作成など) |
| 税金の種類 | 所得税・住民税・個人事業税 | 法人税・法人住民税・法人事業税 |
| 社会保険料 | 任意加入なし → 国保+国民年金(所得次第で年20〜80万円程度) | 社会保険加入が義務 → 健康保険+厚生年金(報酬月額30万円なら年間約110〜120万円、会社と本人で折半) |
| 会計・申告 | 確定申告(青色申告可) 税理士に依頼するなら年間10〜20万円程度 | 決算申告が必須 税理士費用は年間20〜40万円が相場 |
| その他の維持費 | ほぼ不要 | 法人住民税の均等割:年間7万円〜(赤字でも発生) |
| 節税メリット | 青色申告特別控除65万円/専従者給与/経費計上 | 役員報酬の調整/家族を役員にして給与分散/退職金制度など大きな節税策あり |
| 信用力・取引面 | 個人の信用に依存 | 法人格があるため、銀行口座開設や大口取引に有利 |
年間維持コストの目安
- 個人事業主(売上300万円〜500万円規模)
国保+国民年金:約40〜70万円/年
+税理士に依頼するなら10〜20万円程度 - 法人化(同規模の売上・役員報酬300万円想定)
社会保険料:約110〜120万円(会社+個人負担合計)
+法人住民税7万円
+税理士費用20〜40万円
👉 合計すると 法人は個人よりも年間で数十万円〜100万円以上コスト増 になるのが一般的です。
まとめポイント
- 売上が少ないうちは「個人事業の方が圧倒的にコスパが良い」
- 売上が 1,000万円〜2,000万円規模 に到達すると、節税や社会保険メリットを含めて法人化を検討する価値が出てくる
- 法人は「節税効果」と「社会的信用力」が大きなメリット
国保組合に加入する
一部の職業分野では「国民健康保険組合」という仕組みがあり、通常の国保よりも保険料や給付が安定しているケースがあります。
芸能・舞台関係者であれば「文芸美術国民健康保険組合(文美健保)」などが代表例です。演劇や舞踊に携わる人は検討する価値があります。
副業+会社員を続ける
- 本業を会社員として継続していれば、そのまま厚生年金と健康保険に加入し続けられます。
- ダンス収入は副業収入として申告すればよいため、社会保険は会社経由で維持しつつ、フリー活動を並行できます。
👉 フリーランスだからといって必ず「国保+国民年金」だけとは限りません。扶養、法人化、国保組合、副業継続など、ライフスタイルや収入状況に応じて複数の選択肢を検討できるのです。
(出典:厚生労働省「社会保険の加入条件」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html )
ダンサーが意識したいポイント
フリーランスダンサーとして活動する上で、社会保険や年金に関する計画性は欠かせません。特に以下の点を意識しておくと安心です。
- 国保と国民年金の支払いは「前年の収入」で決まる
→ たとえば2024年に収入が大きく増えた場合、その所得を基に算定された国民健康保険料や住民税が2025年に反映されます。翌年の負担を見越し、急な出費に備えて資金を残しておくのが賢明です。 - 国民年金だけでは将来の受給額が少ない
→ 国民年金は老後の生活を支える「最低限の保障」にすぎません。老後資金を充実させるには、国民年金基金やiDeCoなどを活用し、将来の年金額を積み増すことが必要です。これらは節税効果も大きいため、長期的に取り組む価値があります。 - 社会保険に入りたいなら複数の方法を検討
→ 扶養に入る、法人化する、国保組合を利用する、あるいは副業会社員を続けるなど、フリーランスでも複数の選択肢が存在します。自分のライフプランや収入規模に応じて最適な方法を選択することが大切です。
これらを踏まえれば、「思わぬ負担増で生活が圧迫される」「将来の年金が少なくて不安」というリスクを大幅に軽減することができます。安心してダンスに打ち込むためにも、今のうちから社会保険と年金の仕組みを理解し、備えを始めておきましょう。
まとめ
フリーランスダンサーは、社会保険や年金を「自分で管理する」必要があります。
健康や老後の生活に直結する大切な仕組みだからこそ、早めに理解し、準備を始めておきましょう。
👉 税金や保険の知識を持つことは、「安心してダンスを続けるための投資」と考えると良いです。
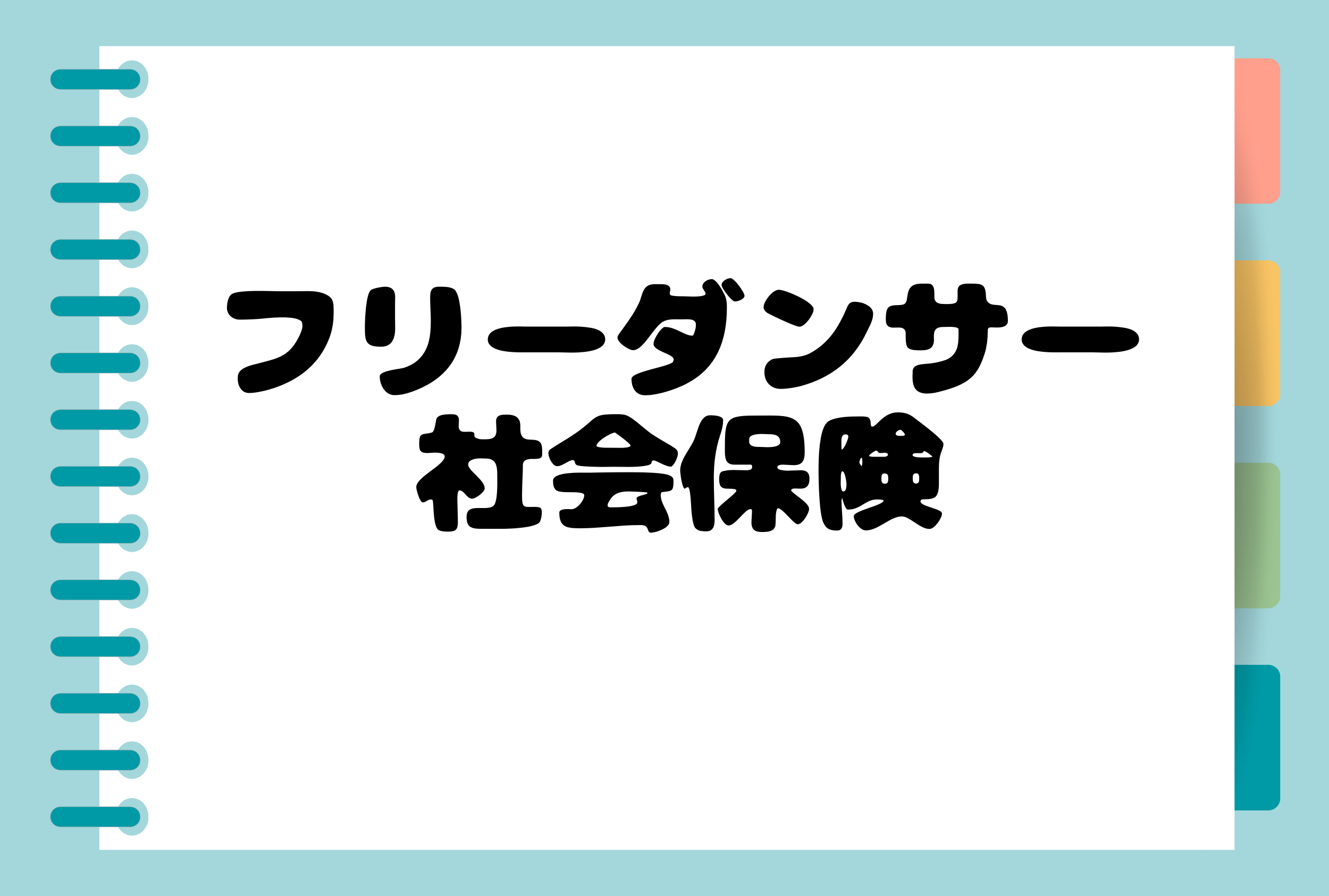
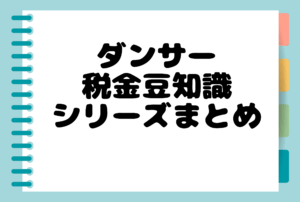
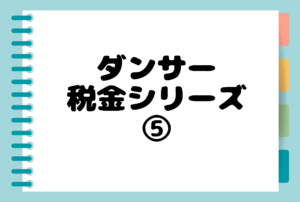
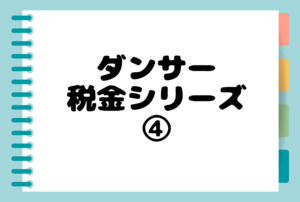
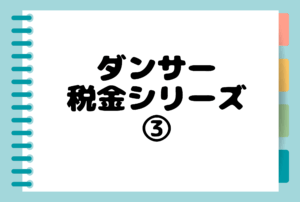
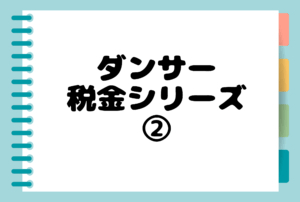
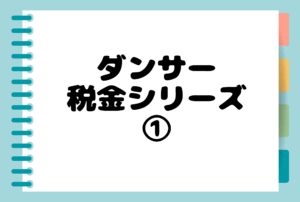

コメント